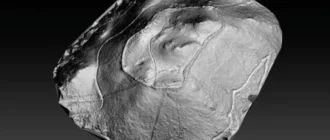最後の氷河期には、アジアから北米への沿岸ルートは非常に危険であったため、人類は、長く危険な旅に適した環境要因のある2つの時期にのみ渡った可能性があることが、新しい研究で明らかになった。
この研究は、2月6日に米国科学アカデミー紀要(新しいタブで開く)で発表された。
この時期、冬の海氷と夏の海氷のない時期には、多様な海洋生物が生息し、北太平洋沿岸を安全に移動できたと考えられる、と研究者は述べている。
新大陸への最初の移住は、大きく分けて2つの説がある。一つは、かつてアジアと北米を結んだ陸橋であるベリンギアが比較的氷のない時代、人々は陸路で新大陸に向かったというものである。しかし、巨大な氷河によって陸路での移動が非常に困難であった1万5000年前以前には、アジア、ベリンジア、北米の太平洋岸で水上交通を利用していたことを示す証拠が増えつつある(新しいタブで開く)。
過去4万5千年の気候変動が、海氷、氷河の面積、海流の強さ、陸上と海上の食糧供給にどのような影響を与えたかを分析し、沿岸ルートが時代によってどの程度有効であったかを調べました。
研究チームは、海氷の変動に関する新しいデータと、海氷、海面水温、塩分、氷に付着したゴミなどの詳細を示すアラスカ湾で以前に採取した堆積物サンプルに基づいて、気候モデルを開発しました。その結果、2,500年にわたる最初のウィンドウと1,600年にわたる第2のウィンドウの2つの時間帯が、年間を通じて沿岸を移動していたことが明らかになった。
この2つの期間には、夏のケルプの森が旅行者の食料を確保するのに役立っただろう。海岸線に張り付いた海氷は比較的平らで安定しているため、古代の狩人たちはその上を歩き、アザラシやクジラなどの獲物を捕獲して冬を越した可能性があると研究者たちは指摘している。
この研究の筆頭著者であるカリフォルニア州メンロパークの米国地質調査所の古海洋学者サマー・プレトリアス氏(新しいタブで開きます)は、「障害となるよりもむしろ、海氷がこの地域の移動と生業を一部促進した可能性を示唆しています」とLive Scienceに語っています。
過去45,000年間の他の時期は、沿岸の移動にあまり適していなかったと思われる。例えば、約18,500年前から16,000年前にかけて、巨大な雪解け水の流れが太平洋に流れ込んだ。この巨大な流れは、かつて北米北東部の大部分を覆っていた巨大氷床の端から押し寄せ、アラスカに沿った北向きの海流の平均強度を2倍以上に増大させたはずである。そのため、太平洋沿岸を南下する船旅はより困難なものとなった。また、氷河の融解により、巨大な氷山が定期的に海上に現れるようになり、沿岸の移動に大きな支障をきたすようになった。
「この研究に参加していないテキサスA&M大学の考古学者であるマイケル・ウォーターズ(新しいタブで開く)は、Live Scienceに次のように語った。"この論文は、沿岸部の移動ルートについても同様のことを行うための良いステップとなる"
将来的には、「過去の気候変動に対応して海洋生態系がどのように変化したかを調べ、異なる時代に沿岸の人々がどのような資源を利用していたかをもっと理解したい」と、プレトリウス研究員は語っている。また、ベリンギア周辺で起こった数百年から数千年にわたる短期間の温暖化現象について、それが特定の移住時期と関連しているかどうかを調べたいとも考えている。
ウォーターズは、「海岸を横断してアメリカ大陸に入ったことが明らかになりつつある」と述べている。"彼らは海岸沿いの移動という仮説を次のレベルにまで高めたのです。よくやった"